この記事で解決できる悩み
- 教職教養・一般教養ってどんな試験なの?
- 教職教養・一般教養の特徴や対策方法は?
- 教職教養・一般教養のない自治体(県)はあるの?
教職教養や一般教養という名前を知っていても、イマイチどんな内容なのか分からないのではないでしょうか。
そこで本記事は、教員採用試験の教職教養と一般教養の違いから対策の仕方まで解説しています。
これから受験対策を始める方はもちろん、勉強方法で悩んでいる方は必見です。
※”いつから勉強を始めればいいか”知りたい方は、こちらの「【2024年度】教員採用試験の勉強はいつから?勉強法を徹底解説」を参考にしてください。
教職教養と一般教養の試験名(呼称)は自治体によって異なります。
- 教養検査(北海道)
- 教職教養(東京都)
- 一般教養・教職専門(神奈川県)
- 総合教養(名古屋市)
- 一般教養(兵庫県)
- 教養試験(福岡県)
なので、試験名だけで何がでるのか決めつけないことが大事。
たとえば、兵庫県の試験名は「一般教養」ですが出題内容は「教職教養+一般教養」なんですよね…。
教員採用試験 教職教養と一般教養の内容
教職教養と一般教養は、教員採用試験の筆記試験の一つです。
まずは、それぞれの内容を解説します。
教職教養
生徒指導や教育関連の法律など、教員として必要な「教育に関する知識や理解を問う」分野です。
主な出題科目
教員採用試験では、次の4科目で構成されます。
- 教育原理
- 教育法規
- 教育心理
- 教育史
生徒指導や学級経営など、教員として必要な教育の考え方や方法に関する分野です。
主な出題範囲は次のとおり。
- 学習指導要領
- 生徒指導
- 道徳教育
- 特別支援教育
- 人権・同和教育
どの自治体でも必須科目であり、問題数も多い特徴があります。
問題例
タップ(クリック)して問題を表示する。

教育原理は、教員として必要な基礎的な知識を問う科目であるため、日頃から教育に関する情報を意識して、知識を蓄積しておくことが大切です。
特徴
一般教養科目に比べて出題数(出題割合)が多いこと。
| 自治体 | 教職教養 | 一般教養 |
|---|---|---|
| 東京都 | 100% | 0% |
| 千葉県 | 90% | 10% |
| 静岡県 | 70% | 30% |
| 広島県 | 100% | 0% |
| 福岡県 | 70% | 30% |
このように自治体にもよりますが、4科目で50%〜80%を占めています。
総合点を上げるには、教職教養の攻略が必要不可欠なので、優先して勉強してください。
一般教養
社会人として必要な基礎学力(中学校から高校までに学んだ国語、数学、理科、社会、英語)を測る分野です。
主な出題科目
教員採用試験では、次の3領域で構成されます。
- 人文科学(国語、英語)
- 社会科学(社会)
- 自然科学(数学、理科)
*音楽や美術、保健体育などの副科目から出題のある自治体もあります。
国語
漢字の読み、書きや読解問題が多く出ています。
内容は簡単なものが多く、出題数も多いので得点源にしてください。
タップ(クリック)して問題を表示する。

英語
主な出題分野は次のとおり。
- 会話文
- 文法・熟語
- 読解問題
レベルは中学レベル〜大学受験レベルまで様々です。
出題範囲は圧倒的に会話文が多いので、単語帳を使いながら会話文特有の表現を理解しましょう。
タップ(クリック)して問題を表示する。

特徴
一般教養は、教職教養に比べて試験科目が多く、出題範囲も広いです。
たとえば、日本史や世界史をイメージするとわかりますが、とんでもない範囲ですよね。
大学受験のとき1科目だけでもキツかったのに両方を勉強しなくてはいけないので出題範囲の広さがわかるはずです。
 ふくなが
ふくなが中学から高校までの6年間で勉強した範囲を1年程度でやり直す必要があるため勉強に苦労している人は多いんですよね…。
とはいえ、どの科目も全範囲から出題されているわけではないので、志望自治体の出題傾向を理解して勉強することが大事。
その他
文部科学省や中教審、教育委員会が出した答申・資料に関する問題です。また、社会的な関心事(国内外の動向やオリンピックなど)や志望先の歴史・郷土人物に関する出題もあります。
主な出題内容
- 令和の日本型学校教育
- 教育振興基本計画
- 学校教育の情報化の推進に関する法律
- キャリア教育
- 〇〇県教育ビジョン
問題例
タップ(クリック)して問題を表示する。
教育時事


ローカル


一般常識・雑学


最近は、教育時事の出題が増えています。
そのため、文部科学省のホームページを見たり、新聞を読んだりして、普段の生活から情報収集をしておきましょう。
以上が、教員採用試験の教職教養と一般教養の内容です。
教員採用試験 教職教養・一般教養の勉強法
教員採用試験の教職教養と一般教養を勉強する具体的な手順を解説します。
- 出題傾向の把握
- 参考書・問題集を覚える
- 優先順位をつけて勉強する
- “全国”の過去問で総復習
- 反復練習(復習)を意識する
STEP①:出題傾向の把握
まずは、受験先の出題傾向を把握しましょう。
なぜなら、教員採用試験は自治体によって試験科目や頻出分野が違うからです。
たとえば、東京都や岐阜県は一般教養(人文・社会・自然科学)からの出題がありません。兵庫県や愛知県の一般教養は、副科目(音楽や美術など)からも出題があります。
無駄な時間や労力を消費しないためにも、出題傾向を把握してから勉強しましょう。
自治体別の出題傾向について、詳しくは次の記事で解説しています。参考にしてください。
STEP②:参考書・問題集を揃える
出題範囲を把握したら、どんどん知識を覚えていきましょう。
オススメの参考書や問題集は、「【2024年版】教員採用試験のオススメ参考書と問題集【選び方も解説】」で紹介していますが、以下の3冊から1冊選べばOKです。
- オープンセサミノート教職教養(一般教養)
- 教職教養(一般教養)らくらくマスター
- 教職教養(一般教養)の要点理解
オープンセサミノートは書き込み式、その他2冊は赤シートで隠しながら読み進めるスタイルなので、自分に合った参考書や問題集を使ってください。
なお、必ず参考書と問題集はセット(同じシリーズ)で揃えましょう。
- セサミノート+オープンセサミ参考書
- らくらくマスター+よく出る過去問224
- 要点理解+演習問題
該当部分やページがリンクしているので勉強効率が違ってきます。
問題集→参考書の順でインプットする
ダメなパターン
理由は単純で、参考書から読んでいたら試験までに終わらないです。
また、活字だけの本では、どこがどういう形式で問われるのか判断できないので無駄な部分まで覚えなくてはいけません。
良いパターン
問題形式は、必要な知識を実践的な形でインプットできるので記憶にも残りやすいです。
参考書は問題集の解答を読むときの参考として、「正解にたどり着くために必要な知識やその周辺部分を読む」という使い方をしましょう。
STEP③:優先順位をつけて勉強する
限られた時間の中で最大のパフォーマンスを発揮するには、問題数の多い科目や頻出度の高い分野から勉強するのがセオリーです。
たとえば、次のような傾向があるとしたらどの科目から勉強するといいでしょうか?
- 教育原理:9問
- 教育法規:4問
- 教育心理:1問
- 教育史:1問
どんなに教育史が苦手でも、出題数の多い教育原理から勉強した方が効率的ですよね。
すべてを勉強して中途半端になるよりも、まずは問題数が多い(配点が高い)科目に重点を置き知識をインプットしていきましょう。
オススメの順番
- 問題数の多い科目
- ❶の中で頻出度の高い分野
- 出題率の高い科目
- ❸の中で頻出度の高い分野
- 自分の得意とする科目・分野
STEP④:全国過去問集でアウトプット
必要な知識を覚えたら、知識の定着と補強のために「全国の過去問」を使い総復習をしてください。
今までの知識がしっかり身についているかの確認に加えて、初見問題への対応や教育時事の知識をインプットできるからです。
- Hyper実践シリーズ(自治体別)
- 全国丸ごと過去問題集(分野別)
この2冊を押さえれば十分です。
繰り返しになりますが、志望自治体の過去問を何回やっても同じ問題は出ないので意味がありません。でも、他自治体で出ていた問題(範囲)はバンバン出てきます。
過去問集の進め方
- 時間を測って真剣に解く
- すぐに答え合わせをする。
- 不正解問題と自信がなかった問題の解説を読む
- 再度、それらの問題を自力で解く
現在の実力確認も踏まえているので本試験だと思って解いてください。でも、点数に一喜一憂する必要はありません。
「できていない知識の把握と習得」が目的だからです。
STEP⑤:反復練習(復習)を意識する
また、勉強において重要なのは先に進むことよりもどれだけ復習をしたかということです。
僕の経験上、どれだけ勉強量を増やしても復習に時間をかけていないと覚えることはできません。僕も勉強時間の7割ぐらいを復習に充てていました。
復習のタイミングは一概ではありませんが、僕は勉強した箇所は3日連続で見るというルールで覚えていきました。要するにその日に解いた問題は短いスパンで3回見るというものです。
| 1日目 | 1~10ページをやる |
| 2日目 | 1~10ページを見直して、11~20ページをやる |
| 3日目 | 1~20ページを見直して、21~30ページをやる… |
とくに重要なのが翌日の復習。
これをしないだけで一気に知識の定着が悪くなります。
記憶の法則で有名なエビングハウスの忘却曲線でも人間の記憶力は翌日にガタ落ちすることが立証されていますからね。
最初のうちはけっこうシンドイですが、1カ月ほど続けてみれば結果が見えてくるので、復習メインを意識して勉強していきましょう。
教職教養・一般教養でよくある質問FAQ
ここでは、よく相談される質問に回答しています。
- 教職教養のみ(一般教養なし)の自治体はありますか?
- 教職教養・一般教養は差がつきやすいって本当?
- 教育時事やローカル問題はどう勉強すればいいですか?
- 教職教養や一般教養の過去問が見たいです。
- オススメの参考書や問題集はありますか?
教職教養のみ(一般教養なし)の自治体はありますか?
実は、教職教養のみ(一般教養なし)という自治体もあります。
令和6年度(2023年実施)時点での、教職教養のみの自治体は次のとおり。
- 岩手県
- 福島県
- 茨城県
- 東京都
- 岐阜県
- 京都府
- 奈良県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 徳島県
- 愛媛県
- 福岡県(小学校のみ)
- 熊本県
- 熊本市
- 宮崎県
この他にも、一般教養の出題は国語や時事のみといったライトな自治体(千葉県や高知県など)もあります。
なお、これらの自治体は対策がしやすい一方で、合格ラインが高くなったり、専門科目の重要度が高かったりする傾向があるため注意が必要です。



科目が減る=簡単とはならないので、安易な選択はやめましょう。
教職教養・一般教養は差がつきやすいって本当?
本当です。
教員採用試験の筆記試験では、教科専門のウエイトが大きく、二次試験でも評価基準になるなど、教職・一般教養よりも重要度が高い傾向にあります。
そのため、以下のような誤解をしている受験者もけっこういます。
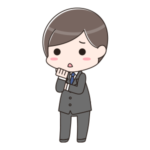
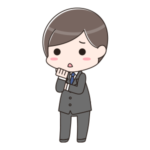
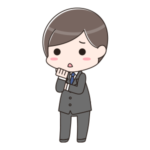
教養で点が取れなくても、専門教科でカバーできるから大丈夫ですよね!
これはとても危険な考え方です。
なぜなら、他のライバルたちも同じく教科専門対策に力を入れるので、「専門はできて当たり前、むしろ差がつくのは教養」という状態が起こるからです。
実際に、教科専門は得意な人が多く、教職・一般教養よりも科目が少ないため、高得点が取りやすい。一方、教職・一般教養はやることが多いため、受験者の中でも確実に差がでてしまうのです。
教育時事やローカル問題はどう勉強すればいいですか?
過去問で対策しましょう。
試験年度より前に出ている答申や資料(旧教育時事)は、どこかしらの自治体で問題として出題されています。
たとえば、令和6年度のトレンド「改訂版生徒指導提要」や「次期教育振興基本計画」は、全国の過去問を使えば対応できます。
しかし、試験年度内に出た教育時事は問題がありません。そこは、一人でたくさんの資料を読み漁るより試験直前期に予備校を活用した方が効率的です。
ローカル問題は、まずは過去問で出そうな資料を教育委員会のHPで探して読みこみましょう。そのうえで、1日完結の予備校講座を活用するなどして対策できます。
| 教育時事(旧) | 全国の過去問で対策 |
|---|---|
| 教育時事(新) | 予備校を活用する |
| ローカル | 志望先の過去問、教育委員会のHP、予備校 |



深入りは厳禁です。資料の冒頭のみ読んでおくといった対策でもいいと思います。
教職教養や一般教養の過去問が見たいです。
教員採用試験の過去問は、次の記事でまとめています。
-300x159.jpg)
-300x159.jpg)
おすすめの参考書や問題集はありますか?
以下の3冊から1冊選べばOKです。
- オープンセサミノート教職教養(一般教養)
- 教職教養(一般教養)らくらくマスター
- 教職教養(一般教養)の要点理解
個人的なオススメはオープンセサミノートです。
オープンセサミノートは書き込み式、その他2冊は赤シートで隠しながら読み進めるスタイルなので、自分に合った参考書や問題集を使ってください。
教員採用試験の参考書について、詳しくは次の記事で解説しています。
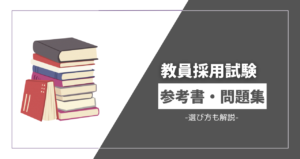
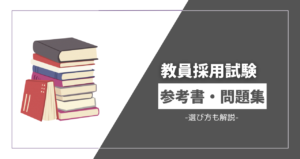
教職教養・一般教養の傾向と対策まとめ
今回は、教員採用試験の教職教養と一般教養の傾向・勉強方法を詳しく解説しました。
まとめると、以下のようになります。
- 科目の多い大学入試共通テスト(旧センター試験)
- 教職教養の出題割合・配点が高くなりやすい
- 一般教養は科目・範囲が膨大
- まずは出題傾向を把握する
- 参考書・問題集はセットで利用する
- 教職教養のみ(一般教養なし)の自治体もあるが難度は高い
- 実は差がつきやすい
教養試験は科目も範囲も膨大ですが、傾向をきちんと理解して勉強すれば十分に対応できるので、やみくもに手をだすのではなく、計画を立てて勉強してくださいね。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
自治体別の出題傾向について、詳しくは次の記事で解説しています。参考にしてください。

















