徳島県教員採用試験の中で特に厄介なのが、今回解説する教職教養。
なんとなく情報を集めて勉強を始めたものの、「結局、何から手をつければいいの?」と悩む方がほとんどでしょう。
そこで今回は、徳島県教員採用試験の教職教養について、試験科目から出題傾向まで徹底解説します。
徳島県教員採用試験の内容は幅広いので、教職教養は効率的・効果的に勉強していきましょう。
【概要】徳島県教員採用試験の教職教養とは?
徳島県教員採用試験の教職教養とは、教育に関する基本的な知識や理解力を測る筆記試験のことです。
校種・教科によって問題が異なる専門教養とは違い、全員が同じ問題を解きます。
教職教養の試験時間と問題数
| 試験時間 | 100分 *専門教科を含む |
|---|---|
| 問題数 | 30問 |
教職教養の出題形式
教職教養の出題形式は択一式と記述式です。
択一式は5つの選択肢の中から、空欄に当てはまる語句の組み合わせを探したり、設問に合致するものを探したりします。

記述式は、空欄に当てはまる語句を書いたり、説明したりすることが求められます。

正確な知識や文字で書かないと正解はもらえません。しっかり、覚えるように、書けるように練習しましょう。
教職教養の配点
教職教養の配点は50点満点です。
1問2〜4点で計算されます。
得点目標は30点以上
得点目標としては、まず「30点以上」というのが第一目標です。合格者の多くがこの程度を取ってきます。
目標は35点。実際は30点程度でOKです。
教職教養の1問に深入りするより、得点が4〜7倍もある専門教養を極めることが大切。くれぐれも科目間の重要性と勉強時間の配分を間違えないように注意しましょう。
教職教養の試験科目
徳島県教員採用試験の教職教養は、教育に関する知識を問う「教職科目」のみで構成されています。
| 教育原理 | 教育の基本的な理念や目的、さまざまな教育理論を問う科目 |
|---|---|
| 教育法規 | 教育に関連する法律や規則の理解力を測る科目 |
| 教育心理 | 学習理論、生徒の発達段階、動機づけや認知のプロセスに関する科目 |
| 教育史 | 日本や世界の教育の変遷、重要な教育改革や教育思想の流れに関する科目 |
 ふくなが
ふくなが2024年度から一般教養科目(人文・社会・自然科学)は廃止になりました!
試験科目は多いので、適当に勉強を始めるのはNGです。
次の科目別出題数を参考にし、どの科目から勉強するのか考えてみましょう。
| 採用年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 教育原理 | 4 | 8 | 8 |
| 教育法規 | 5 | 4 | 7 |
| 教育心理 | 3 | 2 | 9 |
| 教育史 | – | – | 6 |
| 国語 | 3 | 3 | – |
| 英語 | 3 | 3 | – |
| 音楽 | 1 | 1 | – |
| 美術 | 1 | 1 | – |
| 世界史 | – | 1 | – |
| 日本史 | 2 | 1 | – |
| 地理 | 2 | 1 | – |
| 政治 | 1 | 1 | – |
| 国際関係 | 1 | – | – |
| 環境 | – | 1 | – |
| 数学 | 3 | 3 | – |
| 物理 | 1 | 1 | – |
| 化学 | 1 | 1 | – |
| 生物 | 1 | – | – |
| 地学 | 2 | 1 | – |
| その他 | 6 | 7 | – |
- 2024年度から一般教養科目は廃止
- 上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。



全科目からバランスよく出ているんですよね・・・。
教職教養の試験科目について、詳しくは次の記事でも解説しています。初めて教員採用試験を受験する方は参考にしてください。


【徳島県教員採用試験】教職教養の出題傾向
科目によって出題数が違うように、出題分野にも傾向(よく出る・よく出ない)があります。
ここでは、試験科目ごとに出題傾向を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
教育原理の出題傾向
教育原理は、次の12分野で構成されています。
- 教育の意義と目的
- 教育方法
- 学習指導要領
- 道徳教育
- 特別活動
- 生徒指導
- 特別支援教育
- 人権・同和教育
- 社会教育
- 生涯学習
- 学校と学級
- 教育時事
このうち、もっとも出題されている分野は「6.生徒指導」です。過去10年間で9回(17問)出ています。


直近では、5年連続(しかも複数問)出ていることから、今後も引き続き出題されると言えるでしょう。
その他にも「12.教育時事」がよく出題されています。併せて確認してください。
教育法規の出題傾向
教育法規は、次の8分野で構成されています。
- 教育法規の概要
- 日本国憲法
- 教育基本法
- 学校に関する法規
- 学校教育に関する法規
- 児童生徒に関する法規
- 教職員の法規
- 教育行政等の法規
このうち、もっとも出題されている分野は「7.教職員の法規」です。過去10年間で8回(10問)出ています。


直近では5年間で4回出ていることから、今後も引き続き出題される可能性は高いと言えるでしょう。
その他にも「3.教育基本法」がよく出題されています。併せて確認してください。
教育心理の出題傾向
教育法規は、次の6分野で構成されています。
- 教育心理学の歴史や意義
- 発達の理論
- 学習の理論
- 人格と適応
- 学級集団
- 教育評価
このうち、もっとも出題されている分野は「2.発達の理論」です。過去10年間で9回(9問)出ています。


6年連続で出ているので、今後も引き続き出題される可能性が高いです。
その他にも「3.学習の理論」が3年連続で出題されています。併せて確認してください。
教育史の出題傾向
教育法規は、次の7分野で構成されています。
- 西洋教育史(古代・中世)
- 西洋教育史(近世)
- 西洋教育史(近代・現代)
- 日本教育史(古代・中世)
- 日本教育史(近世)
- 日本教育史(近代・現代)
- 西洋・日本総合
このうち、もっとも出題されている分野は「3.西洋教育史(近代・現代)」です。過去10年間で8回(12問)出ています。


2024年度から教職教養のみの出題になったことで、2年ぶりに出題が復活しています。
今後も引き続き出題される可能性が高いので、有名人物を中心に覚えておきましょう。
なお、より詳しい出題傾向を次の記事で解説しています。効率的・効果的に勉強したい方は参考にしてください。
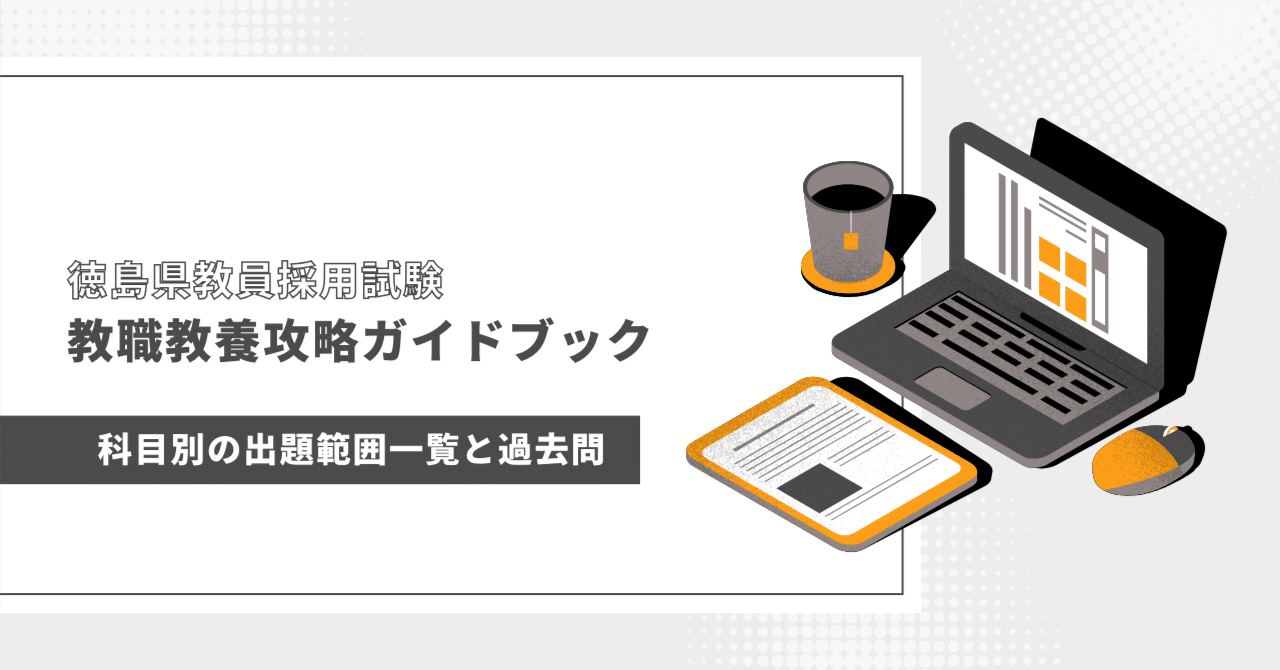
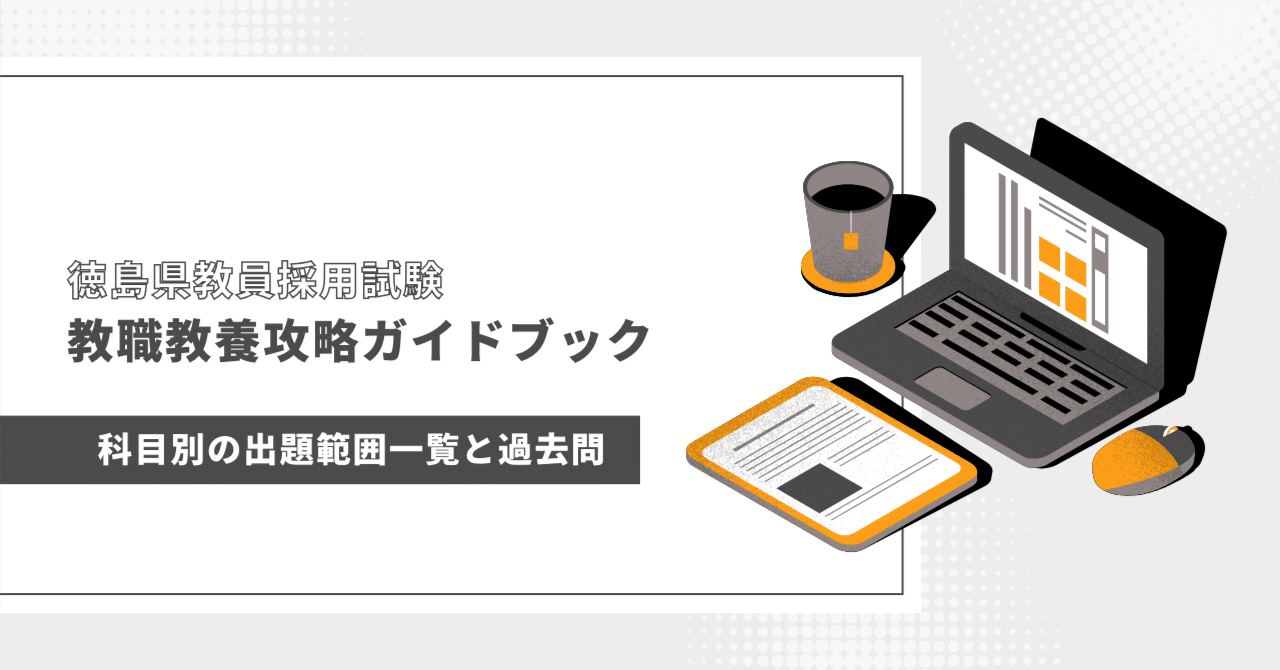
【徳島県教員採用試験】教職教養でよくある質問FAQ
最後に、徳島県教員採用試験の教職教養で、よく相談される質問に回答しています。
教職教養でオススメの参考書・問題集はありますか?
結論、「セサミノート」をオススメします。
セサミノートは、書き込み(穴埋め)式の参考書兼問題集なので、狙われやすい語句やポイントが把握しやすいです。
同シリーズの参考書や問題集も併用して使えば、効率的・効果的に知識を覚えられます。
もちろん、教員採用試験の参考書・問題集は数種類あるので、合う合わないがあります。店頭まで足を運び、自分の目で確かめて、合うものをチョイスしましょう。
教職教養はいつから勉強すればいいですか?
結論、専門教養の勉強がある程度進んだら始めましょう。
なぜなら、専門教養は得意な人が多く、配点は教職教養の4〜7倍もあるからです。早い段階から専門教養対策に集中すれば、点数を取れる可能性が高まりますよね。
とはいえ、教職教養は専門教養と比較して出題範囲が膨大。そのため、完全に後回しにすると試験直前に大量の知識を覚えなくてはいけず詰みます。
したがって、教職教養は専門教養の学習がある程度進んだ後に本格的に取り組むといいでしょう。
教職教養の過去問はありますか?
結論、過去問はあります。
徳島県教員採用試験の過去問題と解答は、県庁ふれあいセンターで閲覧できます。
解説はないので本格的な勉強はできませんが、出題内容の確認だったり、レベルの把握だったりは十分にできます。ぜひ、活用しましょう。



その他に質問があれば、教採ギルド公式LINEより相談してください。
【徳島県教員採用試験】教職教養は独学で勉強できるか
結論、徳島県教員採用試験の教職教養は独学でも十分に勉強できます。
なぜなら、
からです。
初めて目にする科目ばかりなので、決して簡単な試験ではありません。しかし、出題傾向も、参考書も、過去問も、簡単に揃えることができます。
あとは、愚直に勉強するだけ。
したがって、しっかりと対策を行えば独学でも合格点を取れる試験であると言えるでしょう。
今回は以上です。
