名古屋市教員採用試験の一次選考で行われる小論文。
「文章を書く試験でしょ?」と何となく内容を想像するけど、イマイチどんな試験なのか把握できていないのではないでしょうか。
本記事では、名古屋市教員採用試験の小論文に関する下記の内容をまとめています。
- 小論文の概要や傾向
- 小論文の過去問テーマ
- 小論文の対策方法
「名古屋市教員採用試験の小論文を詳しく知りたい」「名古屋市の小論文対策を始めたい」という方は、ぜひ参考にしてくださいね。
※その他、名古屋市の試験情報は「【簡単】名古屋市教員採用試験対策!内容と傾向をわかりやすく解説」でまとめています。
名古屋市教員採用試験 小論文の傾向
名古屋市教員採用試験の小論文は、自分の考えや主張を論理的に説明する文章形式の試験です。
筆記試験(教職教養や専門教科)では判断できない、論理的思考力や読解力、人間性などを総合的に測ることを目的としています。
小論文試験の概要は、以下のとおりです。
| 実施 | 一次試験 |
|---|---|
| 試験時間 | 50分 |
| 文字数 | 制限なし |
| 配点 | A~Dの5段階評価 |
名古屋市教員採用試験 小論文の過去問テーマ
ここでは、名古屋市教員採用試験の小論文の過去問テーマをまとめています。
令和6年度(2023年実施)
「バランス」という言葉から想定されるテーマを想定し、あなた自身の具体的な体験と教育観とを関わらせて論述しなさい。
令和5年度(2022年実施)
「つまずく」という言葉から想定されるテーマを想定し、あなた自身の具体的な体験と教育観とを関わらせて論述しなさい。
令和4年度(2021年実施)
「踏み出す」という言葉から想起されるテーマを設定し、あなた自身の具体的な体験とあなたの教育観とを関わらせて論述しなさい。
令和3年度(2020年実施)
新型コロナウィルス感染症の流行により、社会全体が影響を受け、私たちの生活も変更を余儀なくされています。これらの状況の中で、あなたが強く感じた事をもとにテーマを設定し、その内容をあなたの教育観と関わらせて論述しなさい。
令和2年度(2019年実施)
人との関わりを通して、あなたが成長したと感じた体験を想起してテーマを設定し、その体験とあなたの教育観を関わらせて論述しなさい。
平成31年度(2018年実施)
「変化」という言葉から想起されるテーマを想定し、テーマ設定の理由を記述しなさい。その後、あなた自身の具体的な体験とあなたの教育観を関わらせて論述しなさい。
なお、模範解答例や他のテーマも見たい場合は「【名古屋市教員採用】小論文の過去問テーマと模範解答例」で解説しているので併せて確認してください。
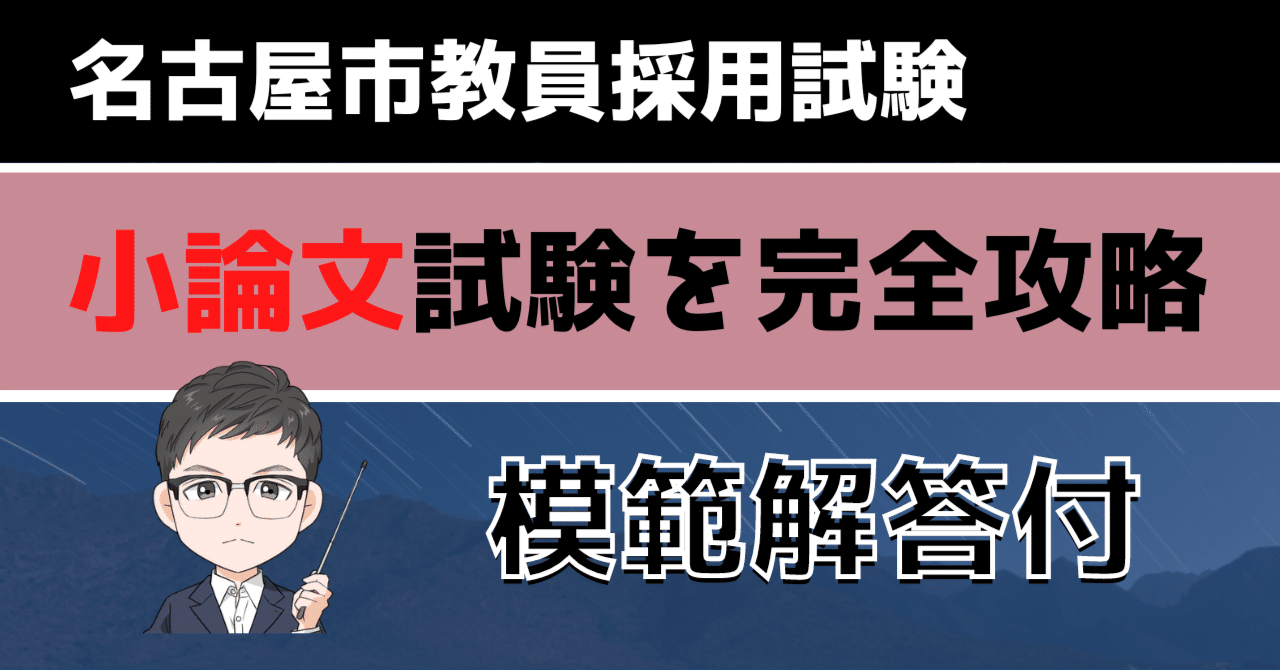
名古屋市教員採用試験 小論文の評価基準
名古屋市教員採用試験の小論文は、以下3つの観点について4段階の採点を行います。
問題意識
テーマと論述内容の着眼点は、自分自身の体験や教育に関わる課題を適切に踏まえたものになっているか。また、自らの思いや考えを述べるとともに、見通しや豊かな発想が見られるか。
教育的資質
文章全体から、教育に対する情熱や使命感、豊かな人間性が感じ取れるか。
表現力
- 文章構成
- 文脈(内容)の展開
- 字句の使い方
これらが適切で、読みやすい論述となっているか。最終的にそれぞれの観点の合計によって、A~Eの5段階で判定します。
 ふくなが
ふくながD以下で不合格(=足切り)なので注意が必要です!
名古屋市教員採用試験 小論文の対策方法
これから小論文の対策をはじめるうえで、「いつから始めればいいんだろう?」と疑問に思うかもしれません。
結論をいえば、対策時期は人によります。
「何を当たり前のことを言っているんだ!」と思うかもしれませんが、事実なので…。
というのも、あなたが文章を書くのが得意と思いこんでいるなら本番1カ月前でもよいかもしれませんし、まったく苦手ならもっと早くやるべきだからです。
まずは今の実力を確認してみる
自分では文章が書けると思っていても、意外に書けなかったり、書けた(気になった)としても課題に対してまったく十分な解答になっていなかったりすることはよくあります。
なので、とりあえず予備校の模試などを受けてみて、今の論文力を把握してから、対策する時期の判断をしてみましょう。



東京アカデミーや時事通信などが模試を実施していますよ!
そこできちんと書けているようであれば、月に1枚~2枚の論文を書くだけでも対策になります。逆にまったく書けないなら基礎からやる必要がありますよね。
3ヵ月前には始めることを推奨
小論文対策はやることが多いです。
- 課題把握力(読解力)
- 文章構成力
- 表現力
- 語彙力
- 教職関連の知識
これらの力は短期間で身につくものではありません。語彙力や教職の知識くらいなら1ヶ月でも何とかなりますが、他の力を短期間で身につけるのは厳しいです。
書き方の勉強→推敲→フィードバック(添削)→繰り返す(最低2回)
こういった順番で勉強することになるので、やはり最低でも3ヶ月は必要だと思って学習スケジュールを組んでみてください。
小論文には、明確な解答がないため独学では限界があります。そのことを踏まえて対策を始めましょう。
なお、小論文の書き方や添削方法は、次の「【模範解答例あり】教員採用試験の小論文とは?書けない理由や対策方法を解説」で詳しく解説しているので、参考にしてください。
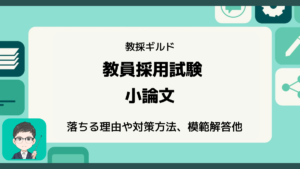
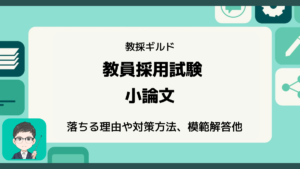
名古屋市教員採用試験 小論文で落ちないために
小論文試験では、どんな人が落ちると思いますか?
答えは、最初から最後まで1人で対策しようとする人です。
小論文で落ちる人ほど、書いたら書きっぱなしってことが多いんですよね…。
答案を書いて誰にも見せないというのは、問題を解いても答え合わせをしないのと同じことです。
過去問を眺めるだけでは、小論文を攻略することはできません。過去問を使って答案を作成し、添削を受けることで徐々に上達します。
小論文が原因で不合格にならにように、早めに(遅くても試験の3ヶ月前を推奨)準備を始めていきましょう。
今回は以上です。
その他、名古屋市の試験情報はこちら!
