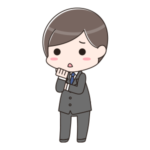 あなた
あなた・教員採用試験の勉強はいつから始めればいいの?
・教員採用試験の勉強は何からすればいいの?
・教員採用試験の勉強方法は?
このような悩みを解決します。
- 教員採用試験の勉強はいつから始めるか。
- 教員採用試験の勉強は何から?
- 教員採用試験の効率的な勉強法とコツ
教員採用試験は、対策することが多いので「いつから勉強すればいいの?」と最初から挫折してしまうケースはとても多いです。
そこで本記事では、初心者が効率よく対策を始められるように具体的な勉強方法や手順(コツ)を解説します。
本記事をしっかり理解すれば「これから教員採用試験の勉強を始める初心者が合格点を取るまでに必要なこと」がすべてわかりますよ!
教員採用試験の勉強はいつから始める?
結論、試験日の1年前(6月〜7月)から勉強を始めるのがベストです!
教員採用試験の内容は幅広く、学業や仕事と両立しながら合格を目指すことになるので、対策が遅くなればなるほど、本試験までに終えることができません。
事実、「試験までに間に合わない」という声は多いです。
現在の学力や目指す自治体・校種教科によって必要な勉強期間は違ってきますが、勉強のスタートが遅いとできることが限られてしまいます。
学校や仕事が忙しすぎてまったく勉強できない時期ができるかもしれませんが、早めに準備をしておけば慌てずに対処できますよね。
大学生1年〜2年生は時間の余裕があるため、早いうちに準備をしたいと思っているかもしれません。
しかし、あまり早く始めても試験内容が変わったり、モチベーションを保つのが難しかったりするのでオススメしません。それよりも部活動やアルバイト、ボランティアなどをやって人生経験を積むことに時間を使いましょう。
詳しくは教員採用試験は大学何年生から勉強する?学年別の対策方法で解説しています。
教員採用試験の合格に必要な勉強時間はどのくらい?
現在の学力や目指す自治体・校種教科によって異なりますが、合格者の多くは600時間程度の勉強をしています。


上記は、2022年度教員採用試験の合格者263名を対象に調査したアンケート結果です。
合格者の約80%が500時間以上の勉強をしている結果となりました。
勉強時間の多さに驚愕したかもしれませんが、1日2時間やれば1年程度で達成できる時間です。1日4時間勉強できるなら半年程度で終わりますね。
| 1日の 勉強時間 | 600時間に達するまでの日数(期間) |
|---|---|
| 2時間 | 300日(約10ヵ月) |
| 3時間 | 200日(約7カ月) |
| 4時間 | 150日(約5カ月) |
| 5時間 | 120日(約4か月) |
| 6時間 | 100日(約3ヵ月) |
基本的には1日2時間勉強として、長期休暇(夏休みや冬休み)にまとめて勉強時間をとったり、試験直前期に勉強時間を増やしたりすると、無理なく勉強時間を確保できるでしょう。
現実的には難しいです。しかし、現在の学力や志望先によっては3ヶ月程度で合格を狙うことはできます。
本試験まで期間・時間が短い場合でも、スケジュールを立てて勉強していくことが大切です。期間別スケジュールの立て方を【間に合わない?】教員採用試験の勉強スケジュールと計画の立て方で解説しています。
教員採用試験の勉強法7ステップ
これから教員採用試験の勉強を始めるときは、次の7ステップで始めましょう。
- 受験先の決定
- 過去問で実力確認
- 参考書・問題集の購入
- 専門科目
- 教職・一般教養
- 小論文
- 人物試験(面接)
STEP1:受験先を決める
まずは、どの自治体を受験するのか決めましょう。
なぜなら、自治体によって試験内容や出題傾向、問題レベルなどが違うからです。
たとえば、東京都であれば、一般教養(人文・社会・自然科学)の出題はありませんが、神奈川県ではたくさん出ています。
| 東京都 | 神奈川県 |
|---|---|
| 教育原理 | 教育原理 |
| 教育法規 | 教育法規 |
| 教育心理 | 教育心理 |
| 教育史 | 教育史 |
| 人文科学(国語や英語) | |
| 社会科学(歴史や政経) | |
| 自然科学(数学や理科) |
必要ない科目を勉強しても時間の無駄です。
また、静岡県は一次試験で個人面接があるのに対して、千葉県では集団面接があります。
| 静岡県 | 千葉県 |
|---|---|
| 教職・一般教養 | 教職教養 |
| 専門科目 | 専門科目 |
| 個人面接 | 集団面接 |
一次試験=筆記試験だと思って勉強ばかりやっていると、面接試験に対応できません。
時間を有効活用するためにも早めに受験先を決めましょう。
教員採用試験の内容は、「【令和6年度採用】教員採用試験の内容一覧を解説【全国66自治体】」でまとめています。
STEP2:過去問を解いて実力確認をする
続いて、志望先の過去問を解きましょう。
なぜなら、最初に過去問を解かないと”何から手をつければいいか”わからないからです。
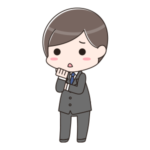
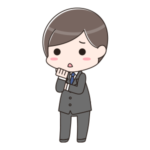
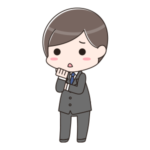
ええ…いきなり過去問!?まだ勉強していないのに解けるわけないじゃん…。
このように思うかもですが、すでに8割以上取れる実力があるのに、中学校レベルの問題集を勉強しても効果はありません。逆に基礎学力がないのに、大学入試レベルの勉強をしても時間の無駄になってしまいます。
なので、勉強を始める前に過去問を解く。そして、現時点の実力に見合った勉強計画を立てていきましょう。
教員採用試験の過去問は、「教員採用試験の過去問はどこでダウンロードできる?最初に使う理由」で数自治体の問題と解答をまとめているので活用してください。
STEP3:参考書・問題集を準備する
続いて、参考書や問題集を揃えましょう。
ポイントは、参考書・問題集を両方揃えることです。
- 参考書:主に知識のインプット
- 問題集:主に知識のアウトプット(必要最低限の知識しか覚えられない)
それぞれ役割が違うので、どちらかに偏った勉強では効果が半減してしまいます。
参考書は、知識量は多いですが、その分無駄も多いです。一方で問題集は必要最低限の知識を覚えるのに適していますが、知識の穴が出てしまうのです。
「問題集で必要最低限の知識を押さえる」→「参考書で周辺知識をカバーする」という流れで勉強を進めるといいでしょう。
オススメの参考書や問題集は、「【2024年版】教員採用試験のオススメ参考書と問題集【選び方も解説】」で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
STEP4:専門科目から始める
優先順位は自治体によって異なりますが、筆記試験は、専門科目>教職教養>一般教養の順で優先度で勉強しましょう。
なぜなら、多くの自治体で専門科目の配点が高いからです。
| 自治体 | 教養試験 | 専門科目 |
|---|---|---|
| 北海道 | 40点 | 100点 |
| 千葉県 | 60点 | 100点 |
| 岐阜県 | 100点 | 400点 |
| 広島県 | 50点 | 200点 |
| 福岡県 | 50点 | 150点 |
このように、教養試験(教職・一般教養)の2~3倍の配点になります。
また、専門科目はどの受験者も点を取ってくるので、点が取れないと、それだけで不利(不合格)になる可能性もあるため注意が必要です。
まずは、配点が高い『教科専門』に7月頃から手をつけていき、12月までにある程度仕上げていきましょう。
専門科目の勉強方法は、「【できないと落ちる】教員採用試験の専門教養が重要な理由と勉強法を解説」を参考にしてください。
STEP5:教職・一般教養
教職・一般教養は、出題傾向を徹底的に理解してから勉強しましょう。
その理由は、科目によって出題数が大きくことなるからです。
| 科目 | 東京都 | 横浜市 | 愛知県 |
|---|---|---|---|
| 教育原理 | 10 | 6 | 6 |
| 教育法規 | 9 | 4 | 3 |
| 教育心理 | 4 | 5 | 1 |
| 教育史 | 1 | 2 | |
| 国語 | 4 | 2 | |
| 数学 | 4 | 2 | |
| 英語 | 2 | 2 | |
| 社会 | 7 | 2 | |
| 理科 | 4 | 2 | |
| ローカル | 1 | 1 |
このように、東京都なら教育原理と教育法規、横浜市なら満遍なく、愛知県なら教育原理から手をつけると効率よく進められそうですね。
また、科目によって出題率も違うため、出題傾向を理解していないと無駄な時間や労力を消費することになります。
- 東京都:100%
- 埼玉県:60%
- 名古屋市:10%
※2013年~2022年実施問題分析データより
なんとなく勉強を始めている人ほど、試験傾向とはかけはなれたことをやっているため、時間をたくさん使っているわりに点数が伸びないので注意しましょう。
教職・一般教養の勉強方法などは、「【問題例あり】教員採用試験の教職・一般教養とは?内容やレベルを徹底解説」を参考にしてください。
STEP6:小論文
小論文試験はテーマに沿って文章を書かせることで、受験者の人間性や論理性、表現力などを見る試験です。
出題テーマは自治体によって様々ですが、「教員としてのあり方」が最も基本的なテーマ。
出題例
子どもにとって魅力ある教師とは(長崎県)
あなたなら学級担任としてどのように学級経営を行っていくか、「学習指導」と「生活指導」について具体的な方策を一つずつ挙げ、それぞれ述べなさい。また、その方策を考える上での問題意識やまとめなどを含めて述べなさい。(東京都)
評価の高い答案を書くには、文章力だけでなく、目指す教師像や教育答申、教育問題など幅広い知識を身につけておくことが大事です。
ここまで紹介してきた筆記試験(教職や専門)とは違い、採点者が評価をつけるため、黙々と勉強するだけでは点数が伸びません。
書いた答案は添削をしてもらい、客観的な意見を取り入れながら勉強することで徐々に結果が見えてくる試験です。
小論文の対策方法などは、「【模範解答例あり】教員採用試験の小論文とは?書けない理由や対策方法」でまとめています。
STEP7:人物試験(面接)
- 個人・集団面接
- 集団討議
- 模擬授業
- 場面指導
- 実技試験
教員採用試験の人物試験は、個人面接をはじめ模擬授業や集団討議まで幅広く行われています。
最近は、教員の資質向上が目標となっていることもあり筆記よりも人物重視の傾向が強いです。
つまり、筆記試験が満点でも、5割でも一次試験を突破してしまえば同じということ。
人物重視であることを理解して、筆記試験の勉強と並行して対策することが重要です。



ここを勘違いして、試験直前まで筆記対策ばかりやって、人物対策を後回しにした結果、落ちる人が多いんですよね…。気をつけましょう!
人物試験(面接)の対策方法は、「【遅いとダメ】教員採用試験の面接練習はいつから?やり方とコツを解説」を参考にしてください。
教員採用試験を効率よく勉強する5つのコツ
短期間(1ヶ月〜3ヶ月)で合格ラインに乗ることは簡単ではありませんが、きちんとコツを理解して勉強すれば充分に闘うことは可能です。
効率よく勉強を進めるコツは以下の5つ。
- ゴールを明確にする
- 頻出分野を理解する
- 捨て科目を上手に使う
- 文章を書いて覚えない
- 復習の回数を意識する
合格ラインを明確にする
合格ラインはまず7割を目標にしましょう。
自動車免許のように9割必要な試験なら満点を目標にすべきですが、7割なら解けない問題があっても問題ないですし、苦手科目があっても大丈夫です。
最初から7割を取るには何をすればいいのか考えると、勉強時間を大きく短縮できますよ。
詳しくは「教員採用試験の合格ラインは何割?合格最低点と基準点を超える3つのポイント」を参考にしてみてください。
頻出分野を勉強する
教員採用試験の出題範囲は広いですが、 頻出分野は全体の2~3割ほど。
たとえば、教育原理は「学習指導要領」の出題率が高いですが、茨城県や名古屋市ではほとんど出題がありません。そのような自治体もあるんですね。
四の五の言わずに全部やればいいじゃないか!と思うかもしれませんが、まったく出ない分野を勉強しても時間と労力の無駄ですよ。
なんとなく勉強を始めている人ほど、試験傾向とはズレたことをやっているため頻出分野を理解してから勉強してください
過去の出題傾向は【非公開情報あり】教員採用試験の対策に役立つnoteで公開しています。
捨て科目・分野を決める
勉強初心者にありがちなのが、何もかも網羅しようとして一通り勉強してしまったり、理解できないところがあると徹底的に調べたりするケースです。
教員採用試験は科目も範囲も膨大なので、逆に嫌気が差して挫折する可能性が高くなってしまいます。
『コツ①合格ラインを明確にする』、『コツ②頻出分野を勉強する』でも解説したように、7割を取るために必要な科目・分野(いる・いらない)をハッキリさせることが重要です。



東大に合格するような人でも、苦手な科目や分野は必ずあります。自分なりに取捨選択をして総合点でカバーしているわけです。試験に出ないところはためらいなく捨てることがきわめて大切!
書いて覚えない
僕自身、書きまくって覚えるスタイルでしたが、様々な勉強法を学んできた結果、とても効率が悪いことだとわかりました。
確かに、五感をフル活用して覚えることは科学的にも実証されています。
しかし、何回も書いて覚えようとする勉強法は、ただ書くことが目的になってしまい、時間を使ったわりに成果が見えにくいんですよね。
ボールペンやノートもどんどん消費していくため、勉強している気にはなりますが、読んで覚えるよりも多くの時間を要するため、多くの科目を捌かなければいけない教採向きではありません。



出題形式はほとんど択一式なので、何となく覚えておくくらいでOK。
ノートは使うべき?
覚えた知識をまとめることで、頭の中を整理できるメリットがあるため誰もが一度はやったことのある勉強法だと思います。
しかし、ノートにまとめる勉強法は知識の整理には役立ちますが、覚えることには適していません。
まとめノートといっても、ほとんどの場合、参考書の丸写しをして汚い参考書を量産しているだけなので効果はあまりないです。
繰り返し勉強して、どうしても覚えられない部分だけを集めたノートを作るくらいにしておくといいでしょう。
詳しくは、「【時間の無駄】教員採用試験の勉強でノートが必要ない理由と活用法」で解説しています、
復習に時間を費やす
勉強できる人ほど復習(繰り返し)に時間をかける習慣を作っています。
どんなことでも繰り返しやっていれば無意識のうちに覚えてしまいます。最もわかりやすいのが、電話番号や自宅の住所です。何度も書いているので忘れませんよね。
これは勉強でも同じことが言えるのですが、多くの人は反復することを拒絶しがちです。
これではどれだけ勉強時間を積んでも記憶が定着しません。勉強できる人とできない人を分ける境界線と言っていいでしょう。
心理的に新しいことをしたい気持ちはわかりますが、合格したいなら1冊を繰り返し読むことが重要と言えます。



点数が低い人ほど、繰り返すことを嫌います。「次は何をすればいいですか?」という質問ばかり。それなのに、実際に問題を出してみても解けないんですよね…。
忘れることを恐れてはいけない
何度も忘れて、覚えてを繰り返すことで記憶が定着していくからです。
- 一度も覚えていない
- 一度覚えたのに忘れてしまった
この2つはまったく意味が違いますからね。
圧倒的に後者のほうが再記憶にかかる時間も減少するし、頭のなかで記憶が整理されるため復習した段階で確実に知識が定着しやすくなりますよ。
記憶が薄れていくスピードを遅らせるためには、「復習&復習&復習」が大切なのです。



知識がインプットできるまで、最低でも5回は反復することを自分の習慣として取り入れてしまいましょう。
教員採用試験の勉強は予備校か独学か?【使い分けが大事】
教員採用試験の勉強を進めるうえで、『予備校を利用すべきか』、それとも『独学で勉強するか』という悩みを抱える方も多いでしょう。
僕自身の意見は「両方を上手に使い分ける」という結論に至ります。
もう少し具体的に言えば、筆記試験は独学、論文や面接は予備校といった感じです。
| 独学 0~10,000円 | 予備校 30,000~300,000円 | |
|---|---|---|
| 金銭面 | 参考書代くらい | |
| 学習環境 | ||
| 問題解決 | 教室講座の場合 | |
| 情報力 | ||
| モチベーション | ||
| 人物対策 |
独学と予備校の大きな違いは金銭面です。
正直、独学なら参考書・問題集・模試代くらいの支出しかないですからね。逆に予備校だと数十万円は飛んでいきます。
もちろん、たくさんの科目・範囲を効率よく勉強できる、教えてもらった方が記憶に残りやすいといったメリットもあるので、今のライフスタイルと相談して復習がきちんとできる環境なら予備校利用の価値はあります。
一方で、論文や面接は第三者目線、それも「教職経験をもった人物に見てもらう」といった部分が超重要!なので、論文や面接はプロを頼った方が効率的です。



学生同士や小さなコミュニティで練習するのも良いですが、きちんとした指導者がいるグループで経験を積んだ方が圧倒的にレベルアップしますよ。
教員採用試験の勉強方法まとめ
- 過去問を解いて現在の実力を知る。
- 過去問分析をして志望自治体の出題傾向を理解する。
- 教科専門試験から重点的に勉強する。
- 教職教養は『教育原理』と『教育法規』を重点的に覚える。
- 一般教養は『国語』、『数学』、『英語』の攻略がポイント。
- 並行して小論文、人物試験の対策を行う。
教員採用試験は科目も範囲も膨大なので、まともに勉強していては試験までに終わることができません。結局、中途半端な状態で試験を受けることになるので落ちてしまいます。
勉強期間は短くても、出題傾向に沿って効率よく勉強すれば十分に得点を重ねることは可能です。
やみくもに勉強するのではなく、出題範囲を把握して効率よく勉強することを心がけてみましょう。
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
.png)